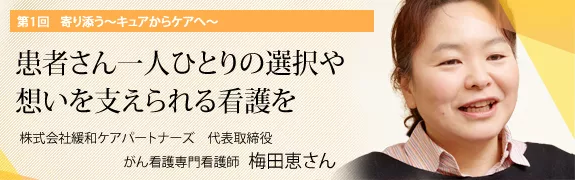
「哲学しながら」の看護
緩和ケアを専門とするがん看護専門看護師の梅田恵さんは、「人を理解する努力を続けてきました」と話す。
「がん」と診断されれば誰しもショックを受けるだろう。頭の中が真っ白になっている患者さんに、たたみかけるように治療法の選択を迫るのではなく、患者さん自身が考え、自分はどうしたいのか、口を開くまであえて見守る。あるいは、治療方針を決めるときも、「仕事と治療の両立はできるのか」「お金はあるのか」「毎日の子どもの世話はどうするのか」といった現実の生活を無視することはできない。それらの課題を聞き、一緒に考え、その人が納得して治療を選べるようにサポートする。「その患者さんの背景にあるものを理解し、気持ちを想像することができなければ、その方にとって適切な対応をすることはできないんです。」
梅田さんが「人を理解する努力」を始めたきっかけは、看護師になって3年目、ホスピス病棟(緩和ケア病棟)に配属されたことだ。それまで一般病棟で次々と入れ替わる入院患者さんに対応していた梅田さんは、「目まぐるしく忙しくて、薬にしても処置にしても一つひとつの意味を考えている暇もなかった」と言う。
「納得しないことはできない生意気なナースだった」と当時を振り返る梅田さんは、「このままで看護師の仕事は続けられない」と、主に末期がんの患者さんが入院するホスピス病棟に移った。そこでは、確かに時間の流れは緩やかになったが、それでも自分の思うような看護ができなかった。
「それまでは時間がないから良い看護ができないと思っていたのですが、本当は自分の勉強が足りないから良い看護ができないんだと、ようやく気づいたんです。」
患者さんのなかには病気を受け入れているように見える人もいれば、受け入れられないままに見える人もいる。そもそも、病気を受け入れる、とかその人らしく過ごすとはどういうことなのか――。「毎日、哲学をしながら看護をするような日々が始まりました。」と、梅田さんは振り返る。


