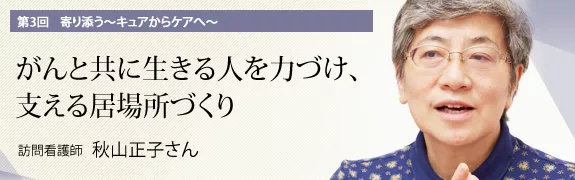
都会の限界集落にある、あたたかい「保健室」
新宿区にある巨大な団地「都営戸山ハイツ」の一階に、「暮らしの保健室」はある。取材にうかがった日、"保健室"は、団地に住む高齢者が健康相談に来ていたり、近所の女性たちが料理を作っていたり、人であふれていた。ちなみに毎週木曜日には、管理栄養士で、がん患者さん向けの料理本も出版している川口美喜子さんが料理を教えに来てくれるという。
そんな「暮らしの保健室」を立ち上げたのは、訪問看護師の秋山正子さん。イギリスの「マギーズ・キャンサー・ケアリング・センター」(以下、マギーズセンター)の話を聞いて、「こんな場所が日本にもほしい!」と感銘を受けたのがきっかけだ。
「こんな場所」とはどんな場所なのかというと、「家庭のような雰囲気のなか、思い思いのスタイルで相談が受けられる場所。」最初にマギーズセンターの話を聞いた4カ月半後、さっそくイギリスまで見学に行くと、がんとともに生きる人を支えるための相談支援の新しい形が、そこにはあった。
「がんかもしれないという不安を抱えている人から、大事な人をがんで亡くして心の傷が癒えない遺族まで、がんの"旅路"のどの時点でも、予約なしでふらっと立ち寄れ、話を聞いてくれて、自分の力や自分らしさを取り戻すのを手伝ってくれる。マギーズセンターはそんな場所でした。」
実際にマギーズセンターを見て「こんな場所を日本にも!」という想いを強くした秋山さんは、マギーズセンターの関係者を日本に呼んで講演会を開いたり、夢の実現に向けて取り組みを進めた。そして、2011年7月、縁あって戸山ハイツに、マギーズセンターをモデルに、相談者自身の力を引き出す手伝いをする暮らしの保健室をオープンした。

ただ、戸山ハイツは、「都会の限界集落」と呼ばれることもあるほど、高齢化が進んだ団地だ。高齢化率は5割を超え、独居率も4割と高い。そのため、がんに限らず、医療も介護も含めて「暮らしに関するよろず相談を行う場」として始まった。
医療や介護の専門家が交代で待機して相談にのるほか、健康に関する勉強会を開いたり、住民同士がお茶を飲みながら話していたり、ボランティアスタッフが話し相手になったり、サロンのような役割も担っている。


